※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること
✓ 物語の導入から結末までの具体的な流れ
✓ 主要な登場人物たちの背景と複雑な関係性
✓ 作品が扱う重いテーマと感動的なメッセージ
✓ 他の読者の感想・評判と文庫本などの実用情報
なぜ、一番近い存在のはずの母と娘は、時としてすれ違ってしまうのでしょうか。
本屋大賞ノミネート作、町田そのこ著『星を掬う』は、そんな普遍的で切実な問いに、真正面から向き合った物語です。
しかし、ただの感動秘話では終わりません。その背後には、DV、若年性認知症、そして世代間で連鎖する「呪い」といった、心をえぐるようなテーマが横たわっています。

この記事では、『星を掬う』のあらすじを「ネタバレなし」と「ネタバレあり」の両面から徹底解説。
物語の骨格となる登場人物たちの紹介から、読者のリアルな感想、タイトルの意味に隠された深い考察、心に刻みたい珠玉の名言まで、あなたが知りたい情報をすべて詰め込みました。
読み終える頃には、この物語がなぜ多くの人の心を掴んで離さないのか、その理由がきっとわかるはずです。
『星を掬う』のあらすじと作品の全体像
10月18日発売予定、『星を掬う』の書影が公開されました。
— 町田そのこ (@sonokosan3939) October 1, 2021
す、すてきーーーー!!
星がキラキラしているところが可愛いと思いませんか。美人にしてもらって嬉しい…。今夜は🍺を🍻します。みんなも遠慮なく飲んでね!! https://t.co/ERA46rdXxO
『星を掬う』がどんな物語なのか、まずはネタバレを気にせず全体像を知りたい方のために、作品の概要から登場人物、読者の感想までをまとめました。
具体的には、次の構成順にてお伝えします。
- 小説『星を掬う』とは?作品の基本情報
- 大まかなあらすじ【ネタバレなし】
- 主な登場人物を紹介
- 感想・レビューまとめ
小説『星を掬う』とは?作品の基本情報
『星を掬う(読み方:ほしをすくう)』は、社会現象にもなった『52ヘルツのクジラたち』で2021年本屋大賞を受賞した作家・町田そのこさんによる長編小説です。
多くの期待が集まる中、受賞後第一作として発表されました。すれ違う母と娘の感動的な再生物語として、再び多くの読者の心を掴んでいます。
現代社会の問題に切り込む、感動の再生物語
本作の大きな特徴は、単なる家族の物語に留まらない点にあります。

町田さんの持ち味である、社会の片隅で生きづらさを抱える人々に寄り添う優しい視点は本作でも健在です。
DVや若年性認知症、ヤングケアラーといった、目を背けたくなるような現代社会の問題にも正面から向き合っています。
これらの重いテーマが、物語に深いリアリティと切実さを与えているのです。その結果、多くの共感を呼び、2022年の本屋大賞にもノミネートされるなど、高い評価を受けました。
作品データ
作品の基本情報は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 著者 | 町田 そのこ |
| 出版社 | 中央公論新社 |
| ジャンル | 小説、文学 |
| 単行本発売日 | 2021年10月18日 |
| 文庫本発売日 | 2024年9月19日 |
| 受賞歴 | 2022年本屋大賞 ノミネート(第10位) |
重厚なテーマを扱いながらも、読後には温かい希望の光を感じさせる物語構成が、本作の大きな魅力といえるでしょう。
読み始めるには少し勇気がいるかもしれませんが、それ以上の感動が待っている作品です。
大まかなあらすじ【ネタバレなし】
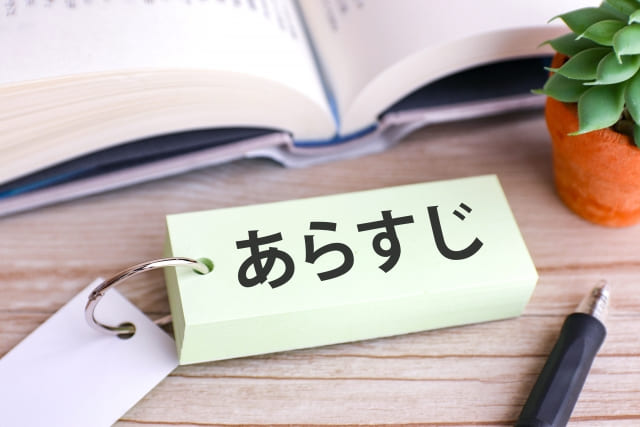
この物語は過去に母親に捨てられたという癒えない傷と、元夫からの執拗なDVに心身ともに蝕まれた主人公・千鶴。
その千鶴が、ひとつの行動をきっかけに自分の人生と向き合い始める再生の物語です。
賞金目当てのラジオ投稿が運命を変える
日々の生活費にも事欠くほど追い詰められていた千鶴は、わらにもすがる思いで、賞金目てに幼い頃の母との唯一の楽しい思い出をラジオ番組に投稿します。
しかし、このささやかな希望を求めた行動が、彼女の人生の歯車を大きく、そして予期せぬ方向へと動かすことになりました。
記憶と違う母との奇妙な共同生活
番組の放送後、千鶴のもとに「自分を捨てた母の“娘”」だと名乗る、美しくも謎めいた女性・恵真から連絡が届きます。
恵真に導かれる形で、千鶴は22年間、その存在を心の奥底で恨み続けてきた母・聖子と再会を果たしました。

ところが目の前に現れた母・聖子は、若年性認知症を患っていました。
千鶴の記憶の中にある“自分を捨てた冷たい母”とは全く違う、脆く、そしてどこか掴みどころのない人物に変わっていたのです。
元夫の追跡から逃れるため、そして母がなぜ自分を捨てたのか、その真実を知るため。
千鶴は、聖子や恵真、そして同じように家族との関係に傷ついた人々が暮らす「さざめきハイツ」での奇妙な共同生活を受け入れます。
心を閉ざした千鶴は、この場所で失われた時間を取り戻し、自分の人生の“星”を掬い上げることはできるのでしょうか。
ここから、痛みを抱えた人々が織りなす、切なくも温かい物語が静かに幕を開けます。
主な登場人物を紹介

『星を掬う』の物語は、それぞれに複雑な過去や悩みを抱えた人物たちが登場することで、より一層深みを増しています。ここでは、物語の中心となる主な登場人物を紹介いたしましょう。
芳野千鶴(よしの ちづる)
主人公。幼い頃に母に捨てられた過去を持ち、自分の不幸を母のせいにして生きてきました。元夫からのDVに苦しんでおり、自己肯定感が低い一面があります。
内田聖子(うちだ せいこ)
千鶴の母親。千鶴を捨てて家を出ましたが、その背景には聖子自身の母親との歪んだ関係がありました。千鶴と再会したときには若年性認知症を患っています。
芹沢恵真(せりざわ えま)
聖子のことを「ママ」と呼び、血の繋がりはないものの娘のように慕う女性です。美容師として働く容姿端麗な人物ですが、壮絶な過去から男性への恐怖心を抱えています。
九十九彩子(つくも あやこ)
「さざめきハイツ」の同居人で、家事全般を担うケアマネージャーです。彼女もまた、過去に自分の娘との関係をうまく築けず、家を出た経験を持っています。
野々原弥一(ののはら やいち)
千鶴の元夫。離婚後も執拗に千鶴を追いかけ、暴力を振るい金銭を奪います。物語における恐怖の象徴的な存在です。
以上、様々な立場の人物たちが「さざめきハイツ」というひとつ屋根の下で関わり合うことで、物語は大きく動いていきます。
感想・レビューまとめ

『星を掬う』は、読了後に深い感動と温かい希望を感じさせると評価される一方で、そこに至るまでの過程が非常に重く、読む人を選ぶという両極端な感想が寄せられている作品です。
心揺さぶる感動と再生の物語(ネタバレ注意)
まず、多くの読者が「感動した」「読んでよかった」と絶賛する理由は、登場人物たちが過酷な状況から再生していく力強い姿にあります。
「母に捨てられた」という一点からしか物事を見られなかった主人公の千鶴。彼女が様々な出会いを経て、母の歪んだ愛情の形を理解し和解していく過程に、涙したという声が多数見られます。
また千鶴が自分の不幸を他人のせいにすることをやめ、「わたしの人生はわたしのものだ」と宣言するクライマックスには、爽快感と共に生きる勇気をもらったという感想も少なくありません。
読むのが辛いという正直な声も
しかし物語の感動に至るまでの道のりは、決して平坦なものではありません。

「読むのが辛かった」という意見もまた、「星を掬う」の正直な一面を捉えています。
元夫・弥一による執拗なDVや、若年性認知症の進行に伴うリアルな介護の描写は特に、読んでいて息苦しさを覚えるほどだといいます。
物語序盤の千鶴が見せる卑屈で攻撃的な態度に、なかなか感情移入できず「イライラしてしまった」という声もあるようです。
これらのポジティブ、ネガティブ双方の感想は、本作が人間の弱さも強さも、醜さも美しさも、一切ごまかすことなく描き切っていることの裏返しといえるでしょう。
「星を掬う」が深く響く人とは
以上の理由から、単に「感動したい」という軽い気持ちで手に取ると、そのテーマの重さに圧倒されてしまう可能性があります。
しかし家族という存在に複雑な思いを抱えている方や、困難な状況から一歩を踏み出すきっかけを探している方もいるでしょう。
そのような方にとっては、苦しい読書体験の先に、かけがえのない何かを見つけられる忘れがたい一冊となるはずです。
町田そのこ 関連記事
『星を掬う』のあらすじをネタバレと考察で深掘り

『星を掬う』の本当の魅力は、その衝撃的な結末と、そこに込められたメッセージにあります。ここでは物語の核心に触れながら、作品をより深く味わうための考察や名言を紹介します。
構成は次のとおりです。
- 結末までの詳細なあらすじ【ネタバレあり】
- 【考察】タイトルに込められた意味とは?
- 心に刻みたい『星を掬う』の珠玉の名言
- よくある質問 (FAQ)
結末までの詳細なあらすじ【ネタバレあり】
この項目では、物語の結末を含む詳細なあらすじを解説します。未読の方はご注意ください。
元夫から逃れるため「さざめきハイツ」での共同生活を始めた千鶴ですが、当初は心を閉ざしたままでした。
若年性認知症を患う母・聖子との間には深い溝があり、自分の不幸をすべて母のせいにして攻撃的な態度をとってしまいます。
母が娘を捨てた本当の理由
しかし物語は、千鶴が同居人たちの過去を知ることで動き出します。
家出して、転がり込んできた彩子の娘・美保が特にそうです。

美保が自分の境遇を棚に上げて母親を責める姿に、千鶴はかつての自分自身を重ね合わせるのです。
この出来事をきっかけに、千鶴は長年囚われていた「悲劇のヒロイン」という自己認識から、一歩引いて自分を見つめ直すようになります。
そして千鶴は母・聖子から、自分を捨てた衝撃的な理由を告白されます。
支配的な愛の連鎖と「一卵性母娘」の呪い
聖子は自身の母親から、「一卵性母娘」と呼ばれるほど支配的な愛情を受けて育ちました。
その苦しみの連鎖を愛する娘には引き継がせたくないという悲痛な思いから、千鶴のもとを去る決断をしたのです。
それは娘を憎んでの行為ではなく、歪んだ形ではあるものの、娘を守るための選択でした。
決別のとき、そして再生へ
そんな矢先、最悪の事態が起こります。
美保がSNSに投稿した写真が原因で、元夫の弥一に居場所を突き止められてしまうのです。
さざめきハイツに乗り込んできた弥一に、千鶴と恵真は再び恐怖で支配されます。
しかしそのとき、認知症で衰弱していたはずの聖子が、ストーブの上の熱いやかんを弥一に投げつけ、娘を守るために命がけで立ち向かいました。
母の決死の愛に背中を押された千鶴は、ついに弥一と対峙し、「わたしの人生はわたしのものだ!」と決別を宣言します。
事件後、千鶴は自分の足で人生を歩み始めることを決意。ラジオ番組で自らの経験を語るという新しい道に進みます。

長年のわだかまりを乗り越え、母と娘として新しい関係を築いていく希望を描いて、物語は幕を閉じます。
【考察】タイトルに込められた意味とは?

『星を掬う』という詩的で美しいタイトルは、この物語の核心を貫く、非常に深く多層的な意味を持っています。
この言葉を理解することで、母と娘が織りなす再生の物語が、より一層心に響くものになるでしょう。
まずこのタイトルが直接的に示しているのは、若年性認知症を患う母・聖子の内面世界です。
作中では、聖子の記憶が広大で暗い海の底に沈んでいく様子が描かれます。
普段はアクセスできなくなった膨大な記憶の中で、ふとした瞬間に、かつての鮮やかで大切な思い出だけが、水面に浮かぶ「星」のようにきらめくのです。
この儚くも美しい情景こそが、「星を掬う」という行為の根幹にあります。
上記の基本的な意味合いを踏まえた上で、タイトルには主に3つの考察ができます。
1. 母・聖子にとっての「星」
第一に、母・聖子にとって掬われる「星」とは、他でもない娘・千鶴との幸せだった記憶です。
物語のきっかけとなる「ひと夏の旅」の思い出や、何気ない日常の象徴であった「うそっこバナナサンド」の記憶などがそれに当たります。
認知症によって多くのことを忘れてしまっても、これらの輝かしい記憶は消えることなく、聖子の中で生き続けていました。
これは聖子が娘を捨てたという罪悪感を抱えながらも、心の奥底では娘を深く愛し続けていたことの、何よりの証拠といえるでしょう。
2. 娘・千鶴にとっての「星」
第2に、この「星を掬う」という行為は、主人公である千鶴の成長物語そのものを象徴しています。
当初、千鶴は自分の人生を不幸という暗闇の海だと捉え、その原因のすべてを母のせいにしていました。
しかし、さざめきハイツでの人々との出会いや母との再会を通じ、千鶴は自らの手で、自分の人生の中から希望や肯定できる部分(星)を見つけ出し、掬い上げることを学びます。
それは賞金目当てで、ラジオに思い出を投稿するという小さな行動から始まり、最終的には自分の人生の主導権を取り戻すという大きな決断へと繋がっていきました。
3. 私たち読者にとっての「星」
そして第3に、このタイトルは私たち読者一人ひとりに向けられた、普遍的なメッセージとしても受け取れます。
誰の人生にも、辛い過去や忘れてしまいたい記憶という「暗い海」は存在するかもしれません。
しかしその中にも必ず、掬い上げる価値のある「輝く星」が沈んでいるはずです。
自分の人生を他人のせいにせず、自らの意志でその星を掬い上げること。それこそが、未来へ向かって歩み出す力になるのだと、この物語は優しく語りかけてくれます。
以上『星を掬う』という言葉は、聖子の記憶、千鶴の再生、そして私たちの人生という3つの次元で響き合う、物語のテーマそのものなのです。
心に刻みたい『星を掬う』の珠玉の名言
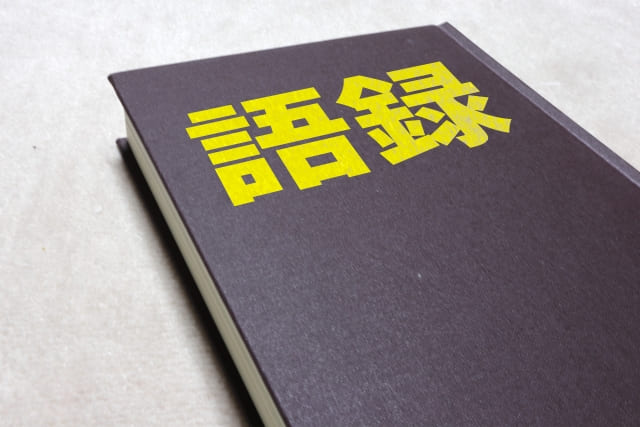
『星を掬う』には、登場人物たちの葛藤や決意が込められた、心に深く突き刺さる言葉が数多く登場します。ここでは、特に印象的な名言をいくつか紹介します。
「わたしの人生は、わたしのものだ!」
これは主人公・千鶴が長年の支配から解放され、自立を宣言する非常に重要なセリフです。
自分の人生の主導権は自分自身で握るという、本作の核心的なメッセージがこの一言に凝縮されています。
「誰かを理解できると考えるのは傲慢で、寄り添うことはときに乱暴となる。大事なのは、相手と自分の両方を守ること」
他人との距離感について、深く考えさせられる言葉です。
良かれと思った行動が、逆に相手を傷つけてしまう可能性を示唆しています。家族であっても個々の人格を尊重し、適切な距離を保つことの大切さを教えてくれます。
「不幸を親のせいにしていいのは、せいぜいが未成年の間だけだ」
医師の結城が、自分の境遇を嘆く千鶴に投げかける、厳しいながらも的確な言葉です。
いつまでも過去や他人のせいにするのではなく、自分の人生に責任を持つべきだという、大人になる上での重要な気づきを与えてくれます。
以上のように、登場人物たちが発する一つひとつの言葉が物語に深みを与え、読者が自身の生き方を見つめ直すきっかけとなっています。
よくある質問 (FAQ)

ここでは、『星を掬う』に関して読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 『星を掬う』の映画化や続編の予定はありますか?
2025年7月現在、『星を掬う』の映画化や続編に関する公式な発表はありません。
ただ著者の別作品『52ヘルツのクジラたち』は2024年に映画化され大きな話題となりました。
本作も本屋大賞にノミネートされるなど評価が非常に高いため、今後の映像化を期待する声が多く上がっています。
※ 「52ヘルツのクジラたち」の詳細は、「小説『52ヘルツのクジラたち』あらすじ徹底ガイド|映画との違いも解説」で取り上げています。
Q2. 文庫本は発売されていますか?
はい、発売されています。2024年9月19日に中央公論新社(中公文庫)から発売されました。単行本よりも手軽に手に取ることができます。書店やオンラインストアで探してみてください。
Q3. 読むと辛くなりますか?
はい、人によっては読むのが辛いと感じる可能性があります。
物語にはDVや若年性認知症の介護といった重いテーマが含まれており、特に序盤はそのリアルな描写に胸が苦しくなるかもしれません。
しかしその辛い展開を乗り越えた先には、温かい感動と希望が待っています。
多くの読者が「最後は救われた気持ちになった」と感想を寄せているため、覚悟して読み進めてみる価値はあるでしょう。
Q4. 『星を掬う』の試し読みはできますか?
はい、電子書籍ストアで試し読みが可能です。
例えば、コミックシーモアやAmazon Kindleなどのサイトでは、物語の冒頭部分を無料で読むことができます。
購入を迷っている方や、物語の雰囲気を先に知りたい方は、まず試し読みをしてみることをオススメします。
「星を掬う」のあらすじがよくわかる要点まとめ

『星を掬う』は、ままならない人生に悩み、立ち止まってしまったすべての人の背中を、そっと押してくれる物語です。それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。
- 著者は『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞した町田そのこである
- DVや若年性認知症など現代社会のリアルな問題を描いている
- 2022年の本屋大賞にもノミネートされた評価の高い作品である
- 主人公・千鶴が母に捨てられた過去とDVに苦しむ再生の物語
- ラジオへの投稿をきっかけに、22年ぶりに母・聖子と再会する
- 主要な登場人物はそれぞれ心に傷を抱えた女性たちである
- 母が娘を捨てた理由は、支配的な愛情の連鎖を断ち切るためであった
- 終盤、母は命がけで娘を元夫の暴力から守る
- 主人公は自分の人生を取り戻すことを決意し、自立への一歩を踏み出す
- タイトルは失われる記憶の中の美しい思い出を掬うことを象徴する
- 物語のテーマが重く、読むのが辛いという意見も存在する
- 読後には希望が感じられ、感動したという感想が多く見られる
- 2024年9月に文庫本が発売されており、手軽に読むことが可能
この記事であらすじや背景を知った今、ぜひご自身の目で、主人公・千鶴が見つけた希望の光と、母・聖子の愛の形を確かめてみてください。あなたの心の海にも、きっと美しい星が輝いているはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトでした。【詳しいプロフィールはこちら】