※【PR】この記事には広告を含む場合があります。
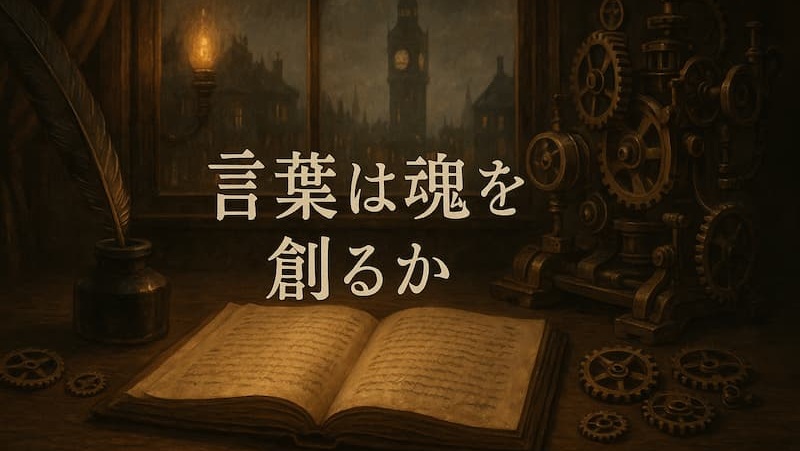
この記事でわかること
- 物語の大まかな流れや詳細なあらすじ
- 原作小説とアニメ映画版の成り立ちや特徴、違い
- ワトソンやフライデーなど主要な登場人物とその役割
- 作品が持つ「意識」や「生と死」などの深遠なテーマ
もし死者が労働力となる19世紀が存在したら? 夭折した天才・伊藤計劃が遺し、盟友・円城塔が書き継いだ奇跡の物語『屍者の帝国』。
主人公ワトソンは諜報員として、屍者技術の根源「ヴィクターの手記」を巡る世界的な冒険へ。「魂とは何か?」 壮大な物語の奥に潜む根源的な問いに迫ります。
この記事ではあらすじ(ネタバレあり)、登場人物、原作とアニメの違い、深遠なテーマを徹底解説。

知的好奇心を刺激する旅へご案内します。
※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。
小説『屍者の帝国』のあらすじ紹介

まずは物語の大筋を掴むために、『屍者の帝国』がどのような作品なのか、その基本的な成り立ちや情報から見ていきましょう。
この章では次の内容を取り上げます。
- 屍者の帝国は三部作のどれにあたる?
- 原作小説の基本情報
- アニメ映画版の基本情報
- 主要登場人物(ハダリー、ニコライ等)
- 簡単なあらすじ(ネタバレなし)
屍者の帝国は三部作のどれにあたる?
夭折の作家・#伊藤計劃 原作小説
— U-NEXTアニメ・マンガ@公式 (@watch_UNEXT_A) November 6, 2024
劇場アニメ化された3作品がU-NEXTに登場。
〚#屍者の帝国〛
〚#ハーモニー〛
〚#虐殺器官〛
<Project Itoh>ここに開幕──https://t.co/BCb9wEPFFn#UNEXTでアニ活 pic.twitter.com/8pOk05pnFY
Project Itohとは
『屍者の帝国』(読み方:ししゃのていこく)は、夭折したSF作家・伊藤計劃(いとう けいかく)氏の著作をアニメ映画化する「Project Itoh」という企画によって制作された三部作のひとつにあたります。
このプロジェクトは伊藤氏の遺した功績を称え、彼の代表的な長編小説を映像化するために立ち上げられました。具体的には、『虐殺器官』、『ハーモニー』、そして本作『屍者の帝国』の三作品が選ばれています。
プロジェクトの体制と作品の独立性
Project Itohは、主にフジテレビの深夜アニメ枠「ノイタミナ」が主導して進められました。
それぞれの作品は独立した物語ですが、伊藤計劃氏ならではの思弁的なテーマや独特の世界観といった点で共通項を見出すことができるかもしれません。
ただし注意点として、三作品のストーリーに直接的な繋がりはありませんので、どの作品から観始めても問題なく楽しめます。
制作スタジオと『屍者の帝国』の特殊性
また制作体制も特徴的で、三作品それぞれを異なるアニメーションスタジオが担当しました。
『屍者の帝国』のアニメーション制作は、『進撃の巨人』などで知られるWIT STUDIOが手がけています。
各スタジオの個性が反映された映像表現の違いも、三部作を比較鑑賞する際の楽しみ方のひとつといえるでしょう。

ちなみに『屍者の帝国』は、伊藤氏自身が完成させた『虐殺器官』や『ハーモニー』とは異なります。
伊藤氏の遺稿を盟友である円城塔(えんじょう とう)氏が書き継いで完成させたという、非常に特殊な成り立ちを持つ作品です。
この制作背景の違いが原作小説、アニメ映画版の双方に独特の個性を与えている要因のひとつと考えられます。
なおプロジェクト当初の予定から制作上の都合により、『虐殺器官』の公開が大幅に遅れるという出来事もありました。
原作小説の基本情報
伊藤計劃と円城塔による「書き継ぎ」
原作となる小説『屍者の帝国』は、2009年に34歳の若さで亡くなったSF作家・伊藤計劃氏が遺したアイデアと冒頭部分の原稿を基に、生前親交のあった作家・円城塔氏が完成させた長編小説です。
そのため純粋な共著というよりは、伊藤氏の構想を円城氏が引き継ぎ、独自の解釈を加えて書き上げた「合作」あるいは「書き継ぎ」作品と表現するのがより正確かもしれません。
伊藤氏が執筆したのはプロローグにあたる30枚ほどの原稿のみで、残りの大部分は円城氏によって紡がれました。この作業は伊藤氏の遺族からの承諾を得て行われました。
刊行情報と多彩なジャンル
この小説は、2012年に河出書房新社から刊行されました。ジャンルとしては、SF(サイエンス・フィクション)に分類されます。
ヴィクトリア朝時代のロンドンを舞台に、蒸気機関と屍者技術が融合したような描写から「スチームパンク」、史実とは異なる歴史を辿る「歴史改変SF」の要素も色濃く持っています。
さらにシャーロック・ホームズのワトソンやフランケンシュタイン博士の怪物、カラマーゾフなど、実在・架空を問わず多くの人物が登場し、重要な役割を担っています。
このように様々な文学作品の登場人物などが登場する点から、本作は「パスティーシュ小説」としての側面も持ち合わせているのです。
物語の概要と受賞歴
物語はフランケンシュタイン博士によって開発された、屍者蘇生技術が世界中に普及し、死者が労働力や兵力として利用されるようになった19世紀末が舞台です。

主人公の医学生ジョン・H・ワトソンが、英国諜報部員として屍者技術の謎を追って世界中を冒険します。
その壮大なスケール、緻密な世界設定、そして「意識とは何か」「生と死の境界はどこにあるのか」といった哲学的な問いは高く評価されています。刊行後には、第33回日本SF大賞特別賞や第44回星雲賞日本長編部門を受賞しました。
読む上での注意点
ただし読む上での注意点も存在します。伊藤計劃氏の持つエンターテイメント性の高い文体と、円城塔氏の博覧強記で思弁的な文体は大きく異なります。
そのためプロローグから本編へと読み進める際に、文体の変化に戸惑いを感じる読者もいるかもしれません。
特に円城氏のパートはその情報量の多さや難解さから、読み応えがある一方で、読みにくさを感じる可能性もあります。
伊藤氏の代表作『虐殺器官』や『ハーモニー』のような読後感を期待して手に取ると、少し印象が異なるかもしれない点は、あらかじめ留意しておくといいでしょう。
アニメ映画版の基本情報
Project Itohの一環としての制作
アニメ映画版『屍者の帝国』は、前述の伊藤計劃氏と円城塔氏による同名の小説を原作として制作されました。2015年に「Project Itoh」の一環として劇場公開されています。
このプロジェクト自体が、伊藤計劃氏の作品群を映像化することを目的としていたため、本作もその流れのなかで企画・制作されました。

アニメーション制作を担当したのは、『甲鉄城のカバネリ』や『SPY×FAMILY』の一部なども手掛けるWIT STUDIOです。
監督は同スタジオで中編アニメーション『ハル』の監督経験がある牧原亮太郎氏が務めました。
またキャラクター原案は、「Project Itoh」の三部作すべてに関わっているイラストレーターのredjuice氏が担当しており、統一感のあるビジュアルイメージを提供しています。
原作からの主な改変点
この映画版の大きな特徴として、原作小説からストーリーや設定に大幅な改変が加えられている点が挙げられます。
例えば、主人公ジョン・H・ワトソンと、彼が蘇生させて旅に同行させる屍者フライデーの関係性は、原作とは異なるよりパーソナルな感情に基づいた描写がされています。
これは二時間程度の映画として物語をまとめ、より多くの観客に分かりやすく伝えるための脚色といえるでしょう。

アクションシーンなども、原作より派手に描かれている印象を受けるかもしれません。
評価と原作比較の推奨
一方でこうした改変については、原作小説のファンを中心に賛否両論の声も聞かれます。
原作のもつ複雑なテーマ性や緻密な設定、文学的な引用の面白さなどが、映画版では簡略化されている。あるいは省略されていると感じる人もいるようです。
特に物語の結末や主要なテーマに対する解釈は、原作とは異なる部分も見受けられます。そのため映画版を観て興味をもった方は、ぜひ原作小説も手に取り、両者の違いを比較してみることをオススメします。

両者の違いを比較すれば、より深く『屍者の帝国』の世界を理解できるはずです。
主要登場人物(ハダリー、ニコライ等)

『屍者の帝国』の壮大な物語は、多くの個性的で魅力的な登場人物たちによって彩られています。ここでは物語の中心となる主要なキャラクターを何人か紹介します。
主人公|ジョン・H・ワトソン
まず主人公はジョン・H・ワトソンです。彼はロンドン大学に通う優秀な医学生でした。
ある出来事をきっかけに英国の諜報機関「ウォルシンガム機関」にスカウトされ、屍者技術の謎を追うことになります。
知的好奇心が旺盛で、物語を通じて「魂」や「意識」の探求に深く関わっていきます。アニメ映画版では、亡くなった親友フライデーを蘇らせたいという強い動機を持つ人物として描かれています。
重要な相棒|フライデー
そのワトソンの重要な相棒となるのがフライデーです。原作小説では、ワトソンに記録係として与えられた青年型の屍者です。
一方のアニメ映画版ではワトソンの親友であり、彼の手によって屍者として蘇生された存在として設定されています。
いずれにしても、彼は単なる記録係に留まらず、物語の核心に深く関わる鍵となるキャラクターです。
協力者|フレデリック・バーナビー
ワトソンの協力者として、フレデリック・ギュスターヴ・バーナビーが登場します。彼は大英帝国陸軍に所属する大尉で、屈強な肉体と行動力を持ち合わせ、ワトソンとは対照的ながら頼れる存在です。
鍵を握る人物|アレクセイ・カラマーゾフ
物語の序盤で重要な役割を果たすのが、アレクセイ・フョードロヴィチ・カラマーゾフです。
ロシア帝国の元従軍司祭で、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に登場するアリョーシャを彷彿とさせます。
彼はアフガニスタン奥地に「屍者の王国」を築き上げ、新型の屍者や、屍者技術の原点とされる「ヴィクターの手記」についての情報を提供します。
ハダリー・リリスとレット・バトラー
ワトソンたちの行く先々に現れる謎めいた存在として、ハダリー・リリスとレット・バトラーがいます。
彼らはアメリカの民間軍事会社ピンカートンに所属しており、ハダリーは美貌の計算者(人造人間のような存在とも示唆されます)、バトラーはその上司です。
『風と共に去りぬ』の登場人物がモデルとされるバトラーは飄々とした態度を見せますが、ハダリーは屍者を操る特殊能力を持つなど、多くの秘密を抱えています。
各国の諜報員|ニコライ・クラソートキン
ロシア帝国の諜報員であるニコライ・クラソートキンも登場します。彼も『カラマーゾフの兄弟』の登場人物(コーリャ少年)がモデルとされ、ワトソンたちとはときに協力し、ときに対立しながら、それぞれの目的のために暗躍します。
物語の中心|ザ・ワン
物語全体の最大の謎の中心にいるのが、「ザ・ワン」と呼ばれる存在です。彼はヴィクター・フランケンシュタイン博士によって創造された最初の屍者であり、人間を超える知性と能力を持っています。
その他の登場人物と注意点
この他にも、ワトソンに指令を与えるウォルシンガム機関の長官「M」。
屍者技術の権威であり『吸血鬼ドラキュラ』でも知られるエイブラハム・ヴァン・ヘルシング教授など、多くの人物が登場します。
これらの登場人物には、実在の歴史上の人物や他の文学作品のキャラクターが大胆に起用されています。

彼らがどのように物語に関わってくるのかも本作の大きな見どころのひとつです。
ただしアニメ映画版では、一部キャラクターの設定や関係性が原作から変更されている場合がある点には留意が必要です。
簡単なあらすじ(ネタバレなし)

舞台設定:屍者技術が普及した19世紀末
『屍者の帝国』は、もしも19世紀に死者を蘇らせる技術が確立されていたら、という大胆な設定のもとで繰り広げられる壮大な冒険物語です。
ヴィクター・フランケンシュタイン博士が開発したとされる「屍者技術」により、死体は「屍者」として蘇り、声を発することはできませんが、労働力や兵力として社会で活用されています。
そのような屍者が存在する、もうひとつの19世紀末の世界が本作の舞台です。
主人公と任務|ワトソンの諜報活動開始
物語はロンドン大学で医学を学ぶ、ジョン・H・ワトソンが主人公です。彼は優秀な頭脳を認められ、英国政府の諜報機関「ウォルシンガム機関」からスカウトを受けます。
彼に与えられた最初の任務は、遠くアフガニスタンの奥地に潜んでいるとされる謎の指導者、アレクセイ・カラマーゾフの実態を調査することです。

あわせて彼が屍者たちで築き上げたと噂される、「屍者の王国」についても調査する必要がありました。
旅の仲間と展開|世界を巡る冒険へ
ワトソンは、記録係として貸与された屍者の青年フライデーをお供に、ボンベイを経由してアフガニスタンへと向かいます。
道中では英国軍人のバーナビー大尉や、ロシア帝国の諜報員ニコライといった人物たちと出会います。
彼らとはときに協力し、ときにはそれぞれの思惑がぶつかり合いながら、危険な旅を続けることになります。
深まる謎|「新型屍者」と「ヴィクターの手記」
旅を進めるなかでワトソンは奇妙な噂を耳にします。
それは従来の屍者とは異なり、まるで生者のように俊敏に動くことができる「新型屍者」の存在。
そしてすべての屍者技術の根源であり、最初の屍者「ザ・ワン」に関する秘密が記されているという「ヴィクターの手記」の存在です。
これらの謎が、ワトソンの冒険をさらに複雑で危険なものへと導いていくのです。
物語の広がりとテーマの示唆
ワトソン一行の旅はアフガニスタンに留まりません。
「ヴィクターの手記」と「ザ・ワン」の行方を追って、一行は明治維新直後の日本、そして発展著しいアメリカ合衆国へと、文字通り世界中を駆け巡ることになります。
壮大なスケールの冒険活劇が繰り広げられる一方で、ワトソンは旅を通じて、
「人間の魂とは一体何なのか」
「生者と屍者を本当に隔てているものは何なのか」
といった、深く根源的な問いと向き合うことになっていきます。
このあらすじは物語の導入部分に過ぎません。
この先ワトソンを待ち受ける驚くべき真実や、複雑に絡み合う陰謀、そして衝撃的な結末については、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

多くの伏線や緻密な設定が散りばめられた、読み応えのある物語があなたを待っています。
屍者の帝国の詳細なあらすじ(ネタバレあり)

この章では次のことを取り上げて、『屍者の帝国』の世界を深く掘り下げます。
- 詳細なあらすじと作品の魅力
- 物語の鍵|ヴィクターの手記とは何?
- 衝撃の結末|フライデーの最後とは
- 深すぎるテーマと魅力を解説
- 作品を彩る豊富な元ネタを紹介
詳細なあらすじと作品の魅力
(注意:この項目は物語の核心に触れるため、ネタバレを含む点はご了承ください。)
アフガニスタンでの依頼と新型屍者の謎
前述のとおり、主人公ワトソンはアフガニスタン奥地で「屍者の王国」の主、カラマーゾフと対面します。そこで彼は、カラマーゾフから驚くべき依頼を受けます。
それはすべての屍者技術の秘密が記されているとされる、「ヴィクターの手記」と、最初の屍者である「ザ・ワン」を追跡することでした。
このときまるで生者のように動く「新型屍者」の正体が、倫理的に許されざる方法。
すなわち生きた人間を強制的に屍者化する技術によって生み出されている可能性が示唆され、物語は一気に不穏な空気を帯び始めます。
世界を巡る手記争奪戦(日本、アメリカ)
「ヴィクターの手記」の行方を追うワトソンたちの冒険は、世界規模へと拡大していきます。

一行は、手記が流出したとされる明治維新直後の日本へと渡ります。
そこでは大里化学という謎めいた企業や、非業の死を遂げたはずの大村益次郎が半ば屍者化したような姿で登場するなど、日本の近代化の裏で蠢く陰謀と屍者技術の闇が描かれます。
さらに舞台はアメリカ合衆国へと移り、ワトソンたちは元大統領ユリシーズ・グラントや、彼が率いるピンカートン社の面々と行動を共にします。
彼らは屍者を意図的に暴走させるとされる謎の組織「スペクター」の調査に協力することになります。しかしそこでも新たな陰謀や、裏切りが待ち受けているのです。
「ザ・ワン」の目的と「魂」の正体
物語が進むにつれて、焦点は最初の屍者「ザ・ワン」の真の目的と、「魂」や「意識」と呼ばれるものの正体へと収斂していきます。
ザ・ワンは人間が漠然と「魂」と認識しているものの実体が、実は特定の「菌株」のような存在であると語ります。そしてこのままでは菌株が不死化し、結果的に人類を破滅に導く可能性があるとも指摘するのです。
彼はその危機を回避するために、世界中の屍者の情報を管理・演算する巨大な「解析機関」そのものと対話し、制御しようと試みていたのです。
クライマックス|ロンドン塔での最終決戦
クライマックスの舞台は、イギリス・ロンドンの象徴であるロンドン塔内部に存在する巨大な解析機関です。
ザ・ワンはついに解析機関との接触を果たしますが、彼の真の目的は人類の救済ではなく、かつて創造主ヴィクターに存在を否定された、自らの「伴侶」を創造することでした。
ザ・ワンの強大な力によって、「屍者の言葉」を理解してしまった解析機関は暴走を開始し、全生命を屍者化しようとします。
この未曾有の危機に対し、ワトソンやハダリーたちは、それぞれの能力と知識を結集して立ち向かうことになります。
魅力1|独創的な世界観とストーリー
『屍者の帝国』の魅力は多岐にわたります。
まず19世紀末という時代設定に、屍者技術というSF的ガジェットを大胆に導入した、壮大で独創的な世界観が挙げられます。
歴史改変SF、スチームパンク、そして世界中を舞台にした冒険活劇の要素が見事に融合しています。
魅力2|パスティーシュとしての面白さ
また作中に散りばめられた豊富なパスティーシュ要素も、大きな魅力です。
実在の人物や、シャーロック・ホームズ、フランケンシュタイン、カラマーゾフの兄弟など、様々な文学作品からの引用が登場人物や設定に組み込まれており、元ネタを知っている読者はより深く楽しむことができるでしょう。
魅力3|深遠な哲学的テーマ
しかし本作の魅力はエンターテイメント性だけではありません。
「意識とは何か」
「魂はどこにあるのか」
「生と死を分かつものは何か」
といった、深く哲学的なテーマを扱っている点も重要です。
物語を通じて、読者自身もこれらの問いについて考えさせられることになります。
魅力4|奇跡的な成り立ちと読書体験
そして何よりも、若くして亡くなった伊藤計劃氏の遺した構想を、盟友である円城塔氏が全身全霊で書き継いだという、その成り立ち自体が奇跡的です。
このふたりの才能の化学反応が、他に類を見ない読書体験を与えてくれます。
読む上での注意点
ただしその特異な成り立ちゆえに、伊藤計劃氏と円城塔氏の文体の違いが気になる読者もいるかもしれません。
また特に円城氏が担当したパートは情報量が多く、哲学的・科学的な考察も深いため、難解に感じられる部分もあります。
一度読んだだけではすべての伏線やテーマを完全に理解するのは難しいかもしれません。

しかしそれだけに、繰り返し読むことで新たな発見がある、奥深い作品であるといえるでしょう。
物語の鍵|ヴィクターの手記とは何?

手記の概要と重要性
「ヴィクターの手記」は、『屍者の帝国』の物語において中心的な役割を果たす、極めて重要なアイテムです。
これは作中世界で屍者蘇生技術を、最初に確立したとされるヴィクター・フランケンシュタイン博士が遺した研究記録です。
その内容を巡って世界中の国家や組織、そして主人公ワトソンたちが争奪戦を繰り広げることになります。
記されていると推測される内容
この手記には単に死体を動かすだけでなく、より高度な屍者技術に関する秘密が記されていると考えられています。
具体的には、すべての始まりとなった最初の屍者「ザ・ワン」を創造した際の詳細なプロセスや、屍者技術の根源となる理論。
さらには失われた「魂」や「意識」の謎に迫る手がかりが含まれているのではないかと噂されているのです。
例えば、作中に登場する「新型屍者」のように、生者に近い動きや反応を示す屍者を生み出す方法。あるいはそれに類する未知の技術が記されている可能性が示唆されます。
争奪の的となる理由
手記を手に入れることができれば、屍者技術を飛躍的に進歩させ、軍事的・経済的に優位に立てるかもしれません。
それゆえに大英帝国やロシア帝国といった大国、アメリカの民間軍事会社ピンカートン、そして物語の黒幕的存在である「ザ・ワン」自身も、それぞれの目的のために手記の行方を血眼になって追っています。
主人公ワトソンもまた当初は任務として、後には自身の探求心から、この手記を追う壮大な旅へと身を投じることになるのです。
情報媒体としての形態
興味深いことに、物語が進むにつれて、「ヴィクターの手記」は必ずしも伝統的な紙媒体の文書ではないことが示唆されます。
ある場面ではそれはパンチカードのような、情報が符号化された媒体として登場します。
これは本作における屍者技術が、単なる生物学的な蘇生術に留まらず、情報工学的な側面を持つという設定を反映しています。

つまり屍者は、「ネクロウェア」と呼ばれるソフトウェアによって制御されているのです。
物語における役割と謎
このように「ヴィクターの手記」は、物語を駆動するマクガフィン(物語を進めるためのきっかけとなる小道具)として機能します。
それだけでなく屍者技術の本質や、「情報」「言葉」「意識」といった本作の核心的なテーマとも深く結びついています。
手記に記された真実とは何なのか、そしてそれがもたらすものは希望なのか絶望なのか。その謎解きが、物語の大きな魅力のひとつとなっています。
ただし手記の完全な内容やその解釈は物語の終盤まで伏せられており、登場人物たちの間でも見解が分かれます。そのため読者自身も、その意味を探りながら読み進めることになるでしょう。
衝撃の結末|フライデーの最後とは

(注意:この項目は物語の結末に関する重大なネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。)
主人公ワトソンと共に旅をし、ときには彼の心の支えともなる屍者フライデー。彼の物語における最後の姿は、多くの読者に衝撃と深い感銘を与え、『屍者の帝国』という作品のテーマ性を強く印象付けるものとなっています。
原作小説におけるフライデーの結末
原作小説の物語は最終章を経て、ふたつのエピローグで締めくくられます。そのふたつ目のエピローグは、他ならぬフライデー自身の視点、彼の内なる「語り」によって描かれているのです。
驚くべきことに彼はワトソンとの三年にも満たない旅の間、記録係としてワトソンの言葉や行動、そして思考を絶えず書き留め続けました。
その記録、つまり「ワトソンの物語」そのものを読み込み、反芻する過程を経て、彼は屍者でありながらにして「意識」を獲得するに至るのです。
これは生前のフライデーの魂が奇跡的に蘇ったという単純な話ではありません。
むしろワトソンという他者が遺した「言葉」や「物語」という情報が、フライデーという身体(ハードウェア)の中で新たな「わたし」という意識(ソフトウェア)を生み出した、と解釈するのが自然でしょう。
意識獲得の意味とフライデーの行動
意識を手に入れたフライデーは、もはやプログラムされた命令に従うだけの存在ではありません。
彼は自らの意志を持ち、かつて自身が記録した「ワトソン」の面影を求め、彼が活躍しているであろうロンドンの雑踏へと、自らの足で歩み出します。
(ただしそのワトソン自身もまた、物語の終わりに大きな変容を遂げ、以前とは異なる存在となっています)
この結末は「言葉」や「記録」、「物語」が持つ創造的な力、そして生者と屍者の境界を問い直す本作のテーマを鮮やかに描き出しています。
またこのフライデーの姿に、夭折した伊藤計劃氏の遺志を継いで物語を完成させた円城塔氏の姿を重ね合わせる読者も少なくありません。

フライデーが最後に発する「ありがとう」という言葉は、様々な解釈を呼び起こす、非常に感動的な一言です。
アニメ映画版における結末の違い
一方で、アニメ映画版におけるフライデーの結末は、原作とは異なる描写がされています。
映画版では、フライデーは元々ワトソンの親友であり、ワトソンが強い願いを持って蘇生させたという設定が加わっています。
クライマックスシーンにおいて、フライデーは暴走しかける自身を抑え、ワトソンを守るかのような行動を見せ、最後には安らかな微笑みを浮かべます。
この描写はワトソンの願いが通じ、生前のフライデーの魂が一瞬現れた。あるいは何らかの形で救済されたかのように解釈することも可能です。
原作のように「記録から意識が生まれる」という明確な描写はなく、より感傷的でドラマティックな結末として描かれています。
フライデーの結末が問いかけるもの
どちらの結末も、フライデーという存在を通して「意識とは何か」「魂の再生は可能なのか」といった根源的な問いを投げかけます。
しかしそのアプローチと提示する答え(あるいは答えの不在)は、異なっています。

原作と映画版、双方の結末を知ることで、より深く『屍者の帝国』の世界について考えることができるでしょう。
深すぎるテーマと魅力を解説
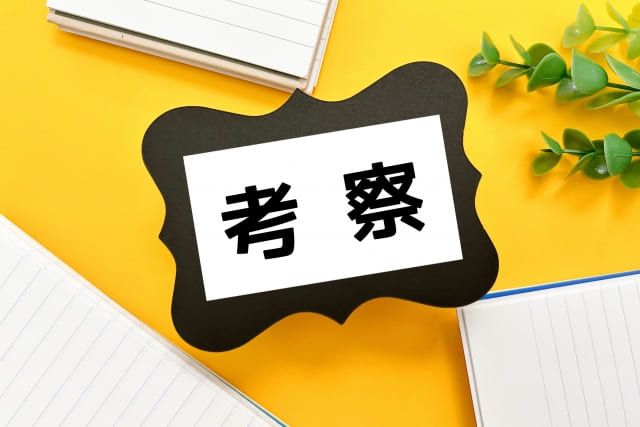
『屍者の帝国』が多くの読者を惹きつけ、高く評価される理由は、単に奇抜な設定や壮大なストーリー展開だけではありません。
その物語の奥底には、現代にも通じる普遍的かつ深遠なテーマが幾重にも織り込まれています。それが読者に知的な刺激と考えさせる時間を与えてくれる点にこそ、本作の真の魅力があるといえるでしょう。
主要テーマ1|「意識」と「魂」の探求
もっとも中心的なテーマは、やはり「意識とは何か、魂はどこにあるのか」という問いです。
屍者が労働力として存在する世界において、生者と死者を隔てるものは何なのか。
作中では、魂には「21グラム」の重さがあるという俗説に触れられたり、あるいは意識の正体は脳に共生する特殊な「菌株」の活動であるという仮説が提示されたりします。
さらに人間の思考や感情は、「言葉」によって規定されるのではないか、という言語哲学的な視点も重要な要素として絡んできます。
これらの様々な角度からの問いかけは、私たち自身の存在の根幹を揺さぶり、普段当たり前だと思っている「自己」や「意識」について、改めて考えさせます。
要テーマ2|「生」と「死」の境界線
これと密接に関連するのが、「生と死の境界」というテーマです。
屍者は本当に「死んでいる」のでしょうか。それともプログラムに従って動くだけの、別の形の「生命」なのでしょうか。
物語に登場する「新型屍者」のように、生前の記憶や能力を一部保持しているかのような存在や、生者を強制的に屍者化する技術は、この境界を極めて曖昧なものにします。
そして主要登場人物たちが迎える結末もまた、従来の生と死の定義では捉えきれない、新たな存在のあり方を提示しているのです。
主要テーマ3|「言葉」と「物語」が持つ力
また伊藤計劃氏が一貫して追求してきた「言葉と物語の力」というテーマも、本作において色濃く反映されています。

物語を動かす鍵となる「ヴィクターの手記」は、まさに言葉で記された情報が持つ力の象徴です。
そして前述のとおり、原作では屍者であるフライデーが「言葉」や「物語」を通じて新たな意識を獲得するという展開があります。これは言葉が単なる伝達手段ではなく、存在そのものを生成しうる力を持つ可能性を示唆しています。
主要テーマ4|「人間」と「技術」の関係性
さらに屍者技術という架空のテクノロジーを通して、「人間と技術の関係性」という現代的なテーマも浮かび上がってきます。
便利な労働力として、あるいは効率的な兵器として技術を利用する。その一方でそれがもたらす倫理的な問題や、人間性の変容、社会構造の変化といった側面が描かれます。
これはAIや遺伝子技術など、現代社会が直面する課題とも重なる部分があり、示唆に富んでいます。
魅力1|パスティーシュとしての深み
加えて、本作が持つ「パスティーシュ」としての側面も、単なる遊び心に留まらない深みを与えています。
実在の人物や様々な文学作品の登場人物・設定を大胆に引用し、再構築することで、既存の物語や歴史の解釈に新たな光を当て、読者の知的好奇心を刺激します。
これらの引用のネットワークを探求することも、本作の楽しみ方のひとつです。
魅力2|伊藤計劃と円城塔による「協奏」
そして最後に本作の成り立ちそのものが、物語のテーマと深く響き合っている点は特筆すべきでしょう。

夭折した伊藤計劃氏の遺志を、盟友である円城塔氏が引き継ぎ、困難な作業の末に完成させたという事実。
それはまさに「死者の言葉」を「生者」が受け取り、新たな「物語」を紡ぎ出すという、本作のテーマを体現しているかのようです。
このふたりの才能がぶつかり合い、融合することで生まれた奇跡的な作品であること自体が、『屍者の帝国』の比類なき魅力なのです。
もちろん、これらのテーマは複雑に絡み合っており、簡単に答えが出るものではありません。だからこそ読者は読み返すたびに新たな発見をし、深く思考する体験を得られるのです。
作品を彩る豊富な元ネタを紹介

元ネタ探求の面白さ
『屍者の帝国』を読み解く上で非常に興味深く、また本作の大きな魅力となっているのが、作中に散りばめられた膨大な数の「元ネタ」です。
これらは実在した歴史上の人物から、世界的に有名な文学作品の登場人物、さらにはSFの古典的なガジェットに至るまで、非常に多岐にわたっています。
これらの元ネタを知ることで、物語の世界観やキャラクターの背景をより深く理解でき、作者たちが込めたであろう遊び心や意図に気づく楽しみも生まれます。
ここではその豊富な元ネタの一部をご紹介しましょう。
主要人物の元ネタ
まず物語の中心となる登場人物たちの多くが、著名な元ネタを持っています。
主人公ジョン・H・ワトソンは、もちろんアーサー・コナン・ドイルが生み出した『シャーロック・ホームズ』シリーズでお馴染みの、ホームズの忠実な相棒であり記録係です。
本作では彼自身が主人公となり、医学生から諜報員へと転身し、世界を股にかける冒険を繰り広げます。
彼に仕える屍者フライデーの名前は、ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』に登場する、主人公に忠実に仕える現地人に由来しています。

ワトソンの頼れる協力者であるフレデリック・バーナビー大尉は、19世紀に実在したイギリスの軍人です。
怪力で知られ、中央アジアを探検した冒険家としての彼の経歴が、作中のキャラクター設定に反映されています。
鍵を握る人物の元ネタ
物語の鍵を握る人物たちにも、印象的な元ネタが見られます。
フガニスタン奥地で「屍者の王国」を築くアレクセイ・カラマーゾフは、文豪ドストエフスキーの代表作『カラマーゾフの兄弟』に登場するアリョーシャが成長した姿として描かれています。
同様にロシア諜報員のニコライ・クラソートキンも、同作のコーリャ少年が成長した姿として登場します。
謎多き美女ハダリー・リリスの名前は、フランスの象徴主義文学『未来のイヴ』(ヴィリエ・ド・リラダン作)に登場する理想的な人造人間ハダリーと、ユダヤの伝承に登場する女悪魔リリスを組み合わせたものと考えられます。
彼女の上司であり、ピンカートン社に所属するレット・バトラーは、マーガレット・ミッチェルの不朽の名作『風と共に去りぬ』の主要登場人物と同じ名前を持っています。
そして屍者技術の権威として登場するエイブラハム・ヴァン・ヘルシング教授は、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』で吸血鬼と戦う博識な人物として有名です。
物語の根幹に関わる元ネタ
物語の根幹に関わる存在にも重要な元ネタがあります。
最初の屍者「ザ・ワン」は、メアリー・シェリーによるゴシック小説の金字塔『フランケンシュタイン』において、ヴィクター・フランケンシュタイン博士によって創造された人造人間(怪物)そのものです。
また、ワトソンが所属する諜報機関の長官「M」は、イアン・フレミングが生んだ『007』シリーズでお馴染みの、ジェームズ・ボンドの上司であるMI6の長官と同じコードネームで呼ばれています。
その他の元ネタ
この他にも、多くの元ネタが物語に登場します。
例えば、屍者蘇生技術の創始者ヴィクター・フランケンシュタイン博士や、実在したエリザベス朝時代の諜報機関をモデルとした「ウォルシンガム機関」です。
さらにアメリカに実在した「ピンカートン探偵社」とその設立に関わったとされるユリシーズ・グラント元大統領、幕末日本で非業の死を遂げたはずの大村益次郎なども重要な役割を果たします。
加えて、コンピュータの父と呼ばれるチャールズ・バベッジが構想した「解析機関」など、挙げていけばきりがないほど多くの元ネタが、物語の随所に組み込まれているのです。
元ネタと物語の関係性
これらの元ネタは、単なる名前の借用やカメオ出演に留まりません。
多くの場合、元ネタの持つ背景や物語が、本作のプロットやテーマ、キャラクターの行動原理と深く結びついています。
例えば、ワトソンが記録者としての性質を持つことや、ザ・ワンが創造主への複雑な感情を抱えていることなどは、それぞれの元ネタを知っているとより深く理解できるでしょう。
元ネタの楽しみ方と注意点
もちろん、これらの元ネタを全く知らなくても、『屍者の帝国』の物語を十分に楽しむことは可能です。
しかしもしあなたが、これらの元ネタに心当たりがあるなら、作中でそれらがどのように引用され、アレンジされているかを発見する「知的な宝探し」のような楽しみ方もできます。
読後に気になった人物や設定について調べてみることで、本作の世界がさらに広がり、新たな発見や驚きが得られるかもしれません。

ただしあまりに元ネタ探しに熱中しすぎると、物語の本筋を見失ってしまう可能性もあるのでホドホドに
『屍者の帝国』あらすじと作品概要まとめ

『屍者の帝国』は、壮大な冒険と「魂とは何か」という深遠な問い、そして伊藤計劃×円城塔による奇跡の合作が生んだ傑作です。
原作とアニメ、それぞれの魅力を比較するのも一興。ぜひこの唯一無二の物語世界を体験してください。それでは、最後にポイントを箇条書きでまとめます。
- 伊藤計劃の作品を映像化するProject Itoh三部作の一つ
- 伊藤計劃の遺稿を円城塔が書き継いだ合作小説が原作
- 原作はSF大賞特別賞や星雲賞を受賞した評価の高い作品
- 屍者技術が普及した19世紀末の歴史改変SF世界が舞台
- シャーロック・ホームズのワトソンが主人公として活躍
- 屍者フライデーはワトソンの記録係であり重要な相棒
- アニメ映画版はWIT STUDIO制作で2015年に公開
- アニメ版は原作から設定やストーリーが一部変更されている
- ワトソンは「ヴィクターの手記」を追って世界を冒険
- 「ヴィクターの手記」は屍者技術の秘密が記された文書
- 最初の屍者「ザ・ワン」が物語の根幹に関わる存在
- 原作のフライデーは言葉と記録から意識を獲得する
- 「意識」「魂」「生と死の境界」が深遠なテーマ
- 言葉や物語が持つ創造的な力が描かれている
- 実在人物や文学作品など豊富な元ネタが散りばめられている
えげつないほどの長文でしたが、最後まで見ていただきありがとうございました。