※【PR】この記事には広告を含む場合があります。
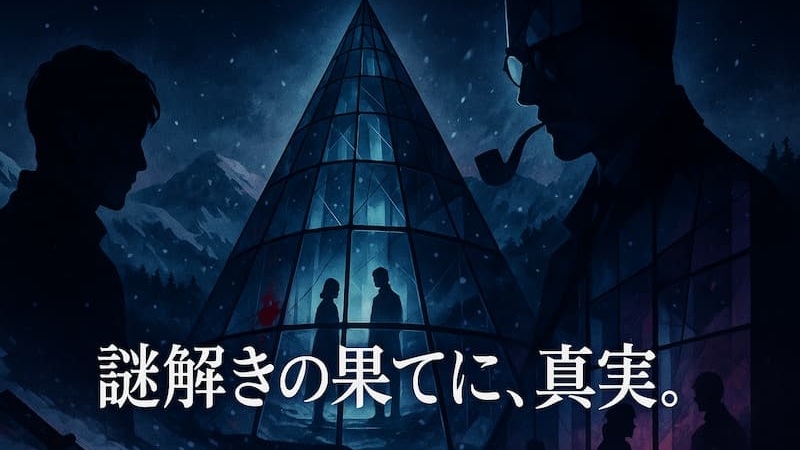
この記事でわかること
- 物語の舞台設定や雰囲気がわかる
- 主要登場人物の関係性や特徴がつかめる
- 名探偵・碧月夜の役割や視点が理解できる
- どんでん返しを含むストーリーの展開が把握できる
雪深い山奥にそびえ立つ、美しくも異様な硝子の塔。そこに招待されたのは、一癖も二癖もある9人の男女と、”名探偵”碧月夜。閉ざされた空間で、医師・一条遊馬による殺人が幕を開ける。
しかしこれは悪夢の始まりに過ぎなかった。次々と起こる不可解な連続殺人、複雑に絡み合う人間関係、そして、あの名探偵自身の暗い過去…。

アナタはこの息詰まる心理戦の果てにある、衝撃の真実に耐えられるか?
犯人は誰なのか、動機は?そして名探偵の正体とは? ページをめくる手が止まらなくなる、極上の本格ミステリの世界へようこそ。
※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。
硝子の塔の殺人 あらすじ(ネタバレあり)
雪深い山奥にそびえ立つ硝子の塔。そこで繰り広げられるのは、招待された9人の男女と、名探偵・碧月夜による、連続殺人事件の謎をめぐる息詰まる心理戦。
この章では、次ことを取り上げます。
- 雪山に建つ硝子の塔が舞台
- 招かれた9人の職業と背景
- 第一の殺人と倒叙ミステリの構造
- 名探偵・碧月夜の異常な執念
- 連続殺人で展開が二転三転
雪山に建つ硝子の塔が舞台
本作の物語は、雪に閉ざされた山奥にそびえる「硝子の塔」で展開されます。外界との接触が断たれたこの場所は、いわゆる“クローズドサークル”の典型です。
こうした密閉空間は登場人物の動きや人間関係を限定し、読者の推理意欲をかき立てる効果があります。登場人物以外の誰も出入りできないため、犯人は必ずそのなかにいるという前提が自然に成立します。
閉ざされた世界の特異性
塔は円錐形のガラス建築という非常に珍しい造りで、視覚的にもインパクトが強く、舞台そのものが作品の象徴ともいえる存在です。さらに塔の構造そのものが、後の事件のトリックに深く関わってきます。
一方でこのような舞台設定には、現実味に欠けるという意見も見受けられます。登場人物が自然災害や事故に遭うリスクも高いため、設定に対する納得感を得るには読者側の想像力が求められるでしょう。
このように雪山の孤立した硝子の塔という舞台は、ミステリ作品の雰囲気を高めるだけでなく、事件の構造そのものにも関係してくる重要な要素となっています。
招かれた9人の職業と背景

硝子の塔に集められたのは、非常に個性的な9名の人物たちです。それぞれの職業や立場には意味があり、物語の謎解きにおいて重要な役割を果たします。
具体的には次の人物です。
- 刑事
- 霊能力者
- ミステリ作家
- 編集者
- 料理人
- メイド
- 執事名探偵
- 医師
ミステリーにおける役割と相互関係
これらの肩書には、ミステリジャンルの伝統的な登場人物像が反映されています。
例えば、刑事は捜査の専門家として、名探偵とは別の視点で事件に関わっていきます。霊能力者はオカルト的要素を、作家と編集者はメタ視点からの語りを担います。
そして医師である主人公・遊馬は、自らの立場を利用して事件に関与することになります。
こうした職業設定は、ただのキャラクターづけにとどまりません。

それぞれの職業が持つ知識や習慣が、推理やトリックの伏線としても機能していきます。
ただし一部のキャラクターは、類型的であるとの指摘もあります。物語に入り込むには、登場人物の背景が描かれる場面をしっかり読み取る必要があるでしょう。
いずれにしても、この9人の存在が物語全体のバランスを取りつつ、ミステリとしての奥行きを生み出しています。
第一の殺人と倒叙ミステリの構造
物語の冒頭で提示されるのは、主人公・一条遊馬による殺人です。この時点で犯人が明かされているため、いわゆる“倒叙ミステリ”という構造を採用しています。
倒叙ミステリとは、犯人が最初からわかっている状態で物語が進行する形式です。読者の関心は「誰が犯人か?」ではなく、「どうやって犯行が暴かれるか?」に移ります。
犯人視点の追跡劇と反転
遊馬は医師としての立場を利用し、館の主・神津島太郎を毒殺します。しかしその直後から、遊馬は名探偵・碧月夜に疑念の目を向けられ、精神的に追い詰められていきます。
こうして読者は、犯人が主人公という設定に緊張感を覚えながら、彼がどのように真相から逃れようとするのかを見守ることになります。
ただし読者の予想を覆す仕掛けも用意されており、この倒叙構造は物語の中盤で一度反転します。そのため単なる形式的な倒叙には留まらず、さらに複雑な展開が楽しめる設計です。
このように第一の殺人は物語の出発点でありながら、その後の展開を加速させる大きな仕掛けとなっています。
名探偵・碧月夜の異常な執念

碧月夜(あおい つきよ)は、本作に登場する“名探偵”であり、物語全体の核ともいえる存在です。月夜の推理力は極めて高く、他の登場人物たちを圧倒します。
しかし注目すべきは、単なる推理の名手ではないという点です。月夜は「名探偵」という存在に異様なまでの執着を持っています。その根底には、幼少期のトラウマや家庭環境が強く影響しています。
「名探偵」への歪んだ憧憬
月夜は、虐待を受けた過去から逃れるためにミステリに没頭し、やがて「名探偵に出会いたい」という願望を肥大化させていきました。
この思いがやがて「自ら事件を起こし、名探偵として事件を解決する」という歪んだ行動に変わっていきます。
遊馬にとっては、月夜の存在はまさに恐怖そのものです。

一見、協力的に見える月夜が、何を考えているかわからない不気味さを持って接してくるからです。
また読者視点でも、碧月夜の言動は終始不安を呼び起こします。ミステリへの愛と狂気が背中合わせで描かれており、名探偵でありながら名犯人でもあるという二面性は、本作の最大の魅力のひとつです。
このように碧月夜は単なる“謎を解く人物”ではなく、物語そのものを根底から揺るがす存在として描かれています。
連続殺人で展開が二転三転
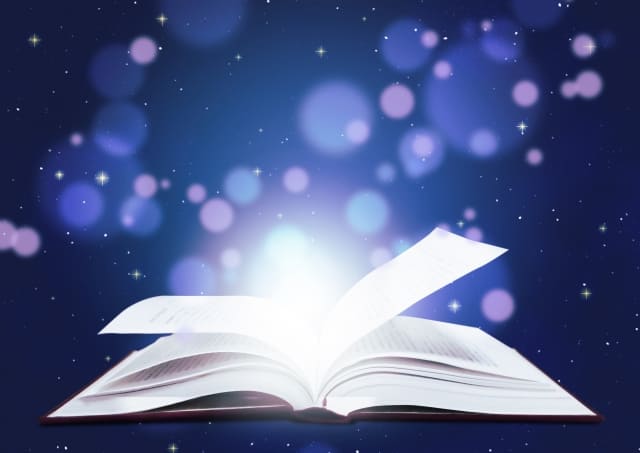
物語の大きな魅力は、連続する殺人事件によって常に状況が変化し、読者の予想を裏切り続ける点にあります。最初の殺人が終わった直後、さらに第二、第三の事件が次々と発生し、物語は混迷を深めていきます。
こうした展開によって、犯人だと思われていた人物の立場が変わったり、伏線だと思われていなかった描写が意味を持ったりと、読者の思考は常に揺さぶられるのです。
複雑に絡み合う人間関係と推理
特に異なる動機や手法で起きる事件が連鎖するため、単なる連続殺人とは異なり、それぞれの事件の背景にも目を向ける必要があるでしょう。
また事件が進むごとに、登場人物たちの関係性にも変化が生まれ、疑心暗鬼が強まっていきます。
推理を進めるためには、過去の出来事や招待客の発言などをつなぎ合わせていく必要があり、読者も自然と考察を深めていく構成です。

一方で展開が目まぐるしく変化するため、ミステリ初心者にとっては少々複雑に感じられるかもしれません。
登場人物や事件の経緯をメモしながら読むと、より理解しやすくなります。
このように、連続殺人によって物語の流れが何度も方向転換することで、最後まで飽きさせない緊張感とスリルが生まれています。
硝子の塔の殺人 あらすじの核心と魅力
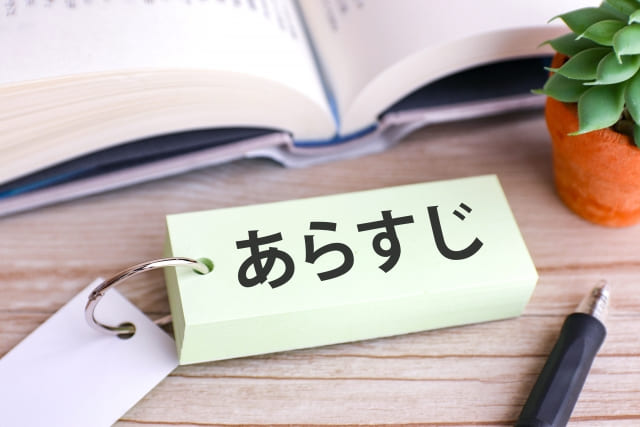
この章では次のことを取り上げて、『硝子の塔の殺人』の世界をさらに深掘りしてきましょう。
- 主人公・遊馬の複雑な立場
- 碧月夜の正体とどんでん返し
- 本格ミステリへのオマージュ多数
- クローズドサークルならではの緊張感
- 読者への挑戦状と真相解明の流れ
- 駄作? 賛否両論の評価と注目点
- 続編や映画化の可能性と今後の展開予測
- 書籍情報と推薦文・文庫版の有無について
主人公・遊馬の複雑な立場
物語の語り手である医師・一条遊馬は、非常に特殊な立ち位置にいます。遊馬は第一の殺人を実行した犯人でありながら、物語の中盤からは探偵役として振る舞い始めるのです。
このような立場は、一般的なミステリ作品ではあまり見られません。自らの罪を隠すために、他の殺人事件の真相を暴こうとする姿勢は、矛盾を抱えた行動にも見えます。
犯人、探偵、そしてワトソン役
しかしこの二面性こそが、遊馬というキャラクターの深みを生んでいます。

さらに遊馬は殺人を犯した理由についても、読者の共感と疑問を同時に引き起こします。
家族への思いや状況的な追い詰められ方などが背景にあるとはいえ、それが許されることなのかという倫理的な問いも残されます。
そしてもうひとつは、遊馬が探偵・碧月夜の「ワトソン役」として彼女と行動を共にすることです。自分の犯行が暴かれるかもしれないという緊張のなかでの協力関係は、見ていてスリリングな要素になっています。
このように、遊馬は単なる「犯人」や「探偵の助手」ではなく、複雑な心理を持ち合わせた語り手として、作品に多層的な視点をもたらしています。
碧月夜の正体とどんでん返し

名探偵として物語を牽引する碧月夜には、大きなどんでん返しが待ち受けています。月夜は読者や登場人物たちから「謎を解く人物」として認識されている一方で、物語終盤には驚くべき真実が明かされます。
具体的には、月夜こそが事件の裏で糸を引いていた「名犯人」だったのです。この事実が判明することで、過去の推理や発言の意味が一変し、それまで積み重ねてきた出来事に新たな解釈が生まれます。
名探偵の仮面と狂気の深層
さらに月夜はただの犯人ではありません。月夜は自身の生い立ちやトラウマを原動力として、名探偵という存在に強いこだわりを持ってきました。
その執念が殺人という行動にまで結びつくという展開は、ミステリとしても人間ドラマとしても非常に濃密です。
ただしこの展開は、やや突飛だと感じる読者もいるかもしれません。名探偵が犯人という構造自体は過去の作品でも用いられてきたため、意外性が薄く感じられる場合もあるでしょう。
それでも、このどんでん返しがもたらす物語の再構築は見事であり、読み終えた後にもう一度最初から読み返したくなる仕掛けになっています。
本格ミステリへのオマージュ多数

『硝子の塔の殺人』は、数多くの本格ミステリ作品へのオマージュが詰まった作品です。
古典から現代までの名作や作家の名前が登場人物たちの会話に登場し、ミステリファンにとっては思わずニヤリとしてしまうような場面が続きます。
例えば、エドガー・アラン・ポーやアガサ・クリスティといったクラシックな作家だけでなく、
- 綾辻行人
- 有栖川有栖
- 島田荘司
といった新本格の旗手たちの作品にも多くの言及があります。登場人物が語るウンチクや分析もまた、作品の魅力の一部として機能しています。
先人への敬意と独自の物語
一方でこれらのオマージュはミステリ初心者にはやや専門的すぎると感じられるかもしれません。特定の作品を読んでいないとピンとこない部分もあるため、少し距離を感じる読者もいるでしょう。
しかしそれでも楽しめるように配慮されており、ミステリに詳しくなくても物語の筋はしっかり追える構成になっています。

あくまでオマージュは味付けであり、物語の本筋に過度に依存しているわけではありません。
このように、過去の名作に対する敬意を込めながら、オリジナルの物語として成立させている点が、本作の特徴のひとつです。
クローズドサークルならではの緊張感

この作品の最大の特徴のひとつが、「クローズドサークル」という設定です。外部と遮断された密閉空間で事件が起こることで、登場人物たちは逃げ場のない心理的プレッシャーにさらされていきます。
特に『硝子の塔の殺人』では、雪深い山中という物理的な隔離だけでなく、塔の構造自体が視覚的にも閉塞感を演出します。こうした環境下では、誰もが疑われ、誰もが疑うという緊張感が生まれます。
またクローズドサークルでは、「犯人がこのなかにいる」という前提が強調されるため、読者の推理心も刺激されやすくなります。
登場人物の発言や行動の一つひとつに注目が集まり、ちょっとした違和感や矛盾もすぐに疑いの目を向けられるのです。
この設定の利点は、読者が舞台のルールや制限をすぐに理解できる点にあります。どこから出入りできるのか、誰がどこにいたのかが限定されているからこそ、トリックや推理の楽しみが成り立つのです。
一方で制約が多いぶん、登場人物の動機や行動に無理があるとすぐに不自然さが露呈してしまいます。そのため読者側にも、鋭い観察力が求められる構成となっています。
読者への挑戦状と真相解明の流れ
物語の中盤には、「読者への挑戦状」という形で、物語世界と現実の読者をつなぐ仕掛けが用意されています。
これは本格ミステリでは伝統的な演出のひとつであり、読者に対して「ここまでで犯人が分かるはずだ」と問いかけるものです。
この構成により読者は単なる傍観者ではなく、名探偵と同じ立場で事件の真相に挑むことになります。
推理への誘いと巧妙な情報操作
犯人は誰なのか、どのように殺人を行ったのか、なぜその犯行に及んだのかという3つの要素が読者自身の考察対象となるのです。
この挑戦状のタイミングも巧妙で、物語がある程度進んだ段階で出されるため、登場人物の関係性や行動の癖、事件の状況が把握できた状態で推理を始められます。
ただし注意点としては、この時点で明らかになっていない情報もあり、すべてを把握するのは不可能に近い構成です。そういった意味では、読者を試しつつも、あえて一部の真実は伏せてあるといえるでしょう。
この演出によって、後半の真相解明シーンはよりドラマチックに映ります。

伏線の回収や意外な真相の明かされ方など、読みごたえのある展開が続きます。
駄作? 賛否両論の評価と注目点

『硝子の塔の殺人』は、多くの読者から高評価を受けている一方で、否定的な意見も少なくありません。このような賛否両論が生まれる理由は、作品の作風が非常に挑戦的であるためです。
評価されている点としては、まず本格ミステリとしての構成力があります。
クローズドサークル、倒叙形式、どんでん返しなど、多くのミステリ要素を盛り込みながらも、一定の整合性を保っている点は高く評価されています。
また登場人物のキャラクター性や、ミステリに対する作者の愛が随所に感じられる点も好意的に受け取られています。
特にミステリ好きの読者からは、「小ネタにニヤリとする」「愛を感じる」といった声が多く見られるようです。
評価の分かれ目|密度と過剰さ
一方で否定的な意見の多くは、「情報量が多すぎて読みにくい」「ミステリ論の引用が浅い」といった指摘に集まっています。
またトリックや動機に、リアリティを感じられなかったという読者もおり、そこに作品全体の評価が左右されるポイントがあります。
つまり作品の密度の高さが評価される一方で、それが読む人によっては「過剰」と感じられてしまう側面があるのです。
読み手の好みによって、受け取り方が大きく分かれる作品といえるでしょう。
続編や映画化の可能性と今後の展開予測
『硝子の塔の殺人』は、その大胆な構成と強烈なキャラクターにより、続編や映画化を期待する声が非常に多い作品です。
特に物語のラストで名探偵・碧月夜が新たな事件を追い求めるような描写があるため、続編を意識した締めくくりであることは明らかです。
実際に作者の知念実希人氏は、SNSなどで「続編の構想が浮かびつつある」と発言しており、前向きに検討していることがわかります。

ただし現時点では、執筆や出版のスケジュールは明かされていません。
そのため正式な続編が登場するには、もうしばらく時間がかかる可能性があります。
映像化への期待と課題
映画化についても、舞台が限定されているクローズドサークル型であることや、登場人物が明確に描かれている点から、映像作品との相性は良好です。
特に碧月夜や一条遊馬といった個性の強いキャラクターが、俳優の演技でどう表現されるかに注目が集まりそうです。
一方で物語に含まれるメタ的な要素や、ミステリーマニア向けのネタが多く、視覚的にどう処理されるかは課題となります。
視聴者にとってわかりやすい脚本構成や演出が求められるため、映像化には慎重なアプローチが必要でしょう。
今後の展開としてはまず文庫化を経て、さらに続編・映像化へと広がる可能性があります。
どの形であれ、この作品の世界観をさらに深める展開が期待されています。ミステリー好きにとっては、次の動きに注目せざるを得ない状況です。
書籍情報と推薦文・文庫版の有無について
【拡散希望❗】
— 知念実希人【公式】 (@MIKITO_777) June 22, 2021
7月30日に発売の『硝子の塔の殺人』の書影が発表されました✨
帯にはなんと
島田荘司先生❗
綾辻行人先生❗
から素晴らしい推薦文を頂きました。
クローズドサークルと化した硝子の尖塔で起こる連続密室殺人。
どこまでも本格ミステリを追求した自信作です。
ぜひお楽しみに🎵 pic.twitter.com/OJgMycexVg
- タイトル:硝子の塔の殺人
- 著者:知念実希人
- ジャンル:本格ミステリ小説(長編)
- 出版社:実業之日本社刊行年2021年
- 価格(税込):1,980円(本体1,800円+税)
- 総ページ数:500ページ超
『硝子の塔の殺人』は、著者の作家デビュー10周年を記念して執筆され、「本格ミステリの集大成」とも呼べる作品に仕上がっています。
物語の舞台は、雪山にそびえ立つ円錐型のガラス製の塔。ここに集められた登場人物たちが、次々と殺人事件に巻き込まれていきます。王道のクローズドサークル、密室殺人、そして多層的などんでん返しが巧みに組み込まれ、読み進めるたびに驚きが待っています。
豪華作家陣からの賛辞と文庫化への期待
帯には、有栖川有栖による「まるで本格ミステリのテーマパーク」との推薦コメントがあり、読者の期待を高めています。
また巻末には島田荘司による特別寄稿も収録されており、ジャンルを代表する作家からの賛辞が本作の完成度を裏付けています。
なお現在のところ文庫版は未発売です。文庫化を望む声は多く、読者の間でも「手元に置いておきたい」「再読したい」との要望が強くあります。
このように、ミステリ初心者から長年の愛好者まで幅広い層に評価されている本作は、物語性と構成力の両面において高い完成度を誇る作品です。

500ページ超えの長編ながらテンポがよく、最後まで飽きさせません。
まだ読んでいない方は、まず単行本版での読了をオススメします。
「硝子の塔の殺人 あらすじ」を総括ポイントまとめ

『硝子の塔の殺人』は、王道と異端が融合した本格ミステリ。クローズドサークルや倒叙、どんでん返し…
名探偵の狂気が、読者を翻弄。緻密な伏線、驚愕の真相は、賛否両論を呼ぶ濃密な読書体験をもたらします。
最後に、あらすじや考察などのポイントを箇条書きでまとめます。
- 豪華なガラスの塔に招かれた作家たちが事件の舞台となる
- 主人公はミステリー作家であり、招待客の一人として塔に集う
- 閉ざされた環境の中で殺人事件が発生する
- 招待客全員に秘密があり、疑惑が錯綜する
- 被害者は塔の主であり、事件の鍵を握る人物でもある
- 密室トリックが物語の重要な要素となっている
- 登場人物の過去が徐々に明かされ、動機が浮かび上がる
- 物語は章ごとに視点が変わり、読者の推理を刺激する構成
- 誰が真犯人なのか分からない緊張感が持続する
- 作中で登場人物がミステリーの定石について語るメタ要素も含まれる
- 真相は予想外の展開で明かされ、読後感に驚きがある
- ミステリー好きにはたまらない伏線と仕掛けが散りばめられている
それでは最後まで見ていただき、ありがとうございました。
- 芥川賞・直木賞・本屋大賞の関連記事
- ≫ 『汝、星のごとく』あらすじ・ネタバレ徹底解説!切ない愛と人生の物語に涙…
≫【推し、燃ゆ あらすじ】21歳芥川賞作家が描く推し活のリアルと現代の光と影
≫ むらさきのスカートの女 あらすじ・解説|犯人は誰?「わたし」の正体とは…
≫ サラバ!あらすじ|なぜ感動?面白くない?読者の評価と深いテーマを解説
≫『ともぐい あらすじ』 河﨑秋子が描く生命の根源|直木賞選評は?
≫『地図と拳』あらすじ完全版|衝撃の結末と伏線を徹底解説【ネタバレ注意】
≫ 東京都同情塔 あらすじと書評|AI時代の言葉の価値を問う芥川賞受賞作の衝撃
≫ しろがねの葉 あらすじ|過酷な運命を生きる女性の物語【直木賞受賞作】
≫ 藍を継ぐ海 あらすじ|舞台はどこ?モデルとなった場所を徹底解説
≫ 苦役列車 あらすじと感想|西村賢太の壮絶な人生が反映された私小説
≫ スクラップアンドビルド あらすじ|「死にたい祖父」「生かしたい孫」の物語
≫ 【黒牢城 あらすじ】黒田官兵衛が挑む、戦国最大の密室ミステリーを徹底解説
≫ 『星落ちてなお』あらすじ|直木賞受賞作が描く、女性の生き方と選択
≫ 鍵のない夢を見る あらすじ・登場人物・ドラマ版との違い【完全解説】
≫ サンショウウオの四十九日 あらすじ|医師が描く、究極の「個」と「生」
≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅